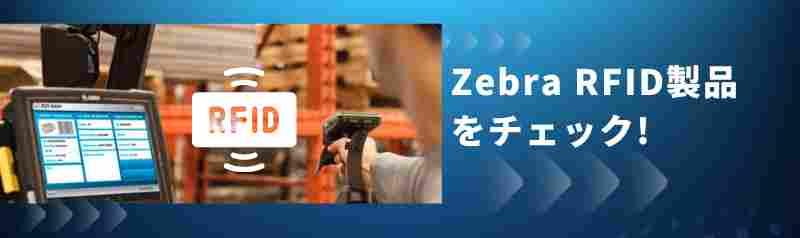- Home
- バース予約システムを入れれば即、 荷待ちは解消!? ~いやあ…そんな甘いもんちゃうで!~
バース予約システムを入れれば即、 荷待ちは解消!? ~いやあ…そんな甘いもんちゃうで!~
物流ジャーナリスト・キクタの連載コラム<あるある! 物流カン違い>物流分野に漂う22の勘違いを正す!
(2025.7.15)

私は尾張の出身で、関西弁ネイティブではない。けれどかつて半年ほど大阪に赴任し下町の取材に回っていた時、懸命に口調をまねた(東京弁では浮いてしまうので)経験がある。なので今でもツッコミを入れたいときはつい、関西弁が口に出る。ツッコミにこれほど適した言語を私は知らない。まあ「そんな甘いもんちゃうで!」が正しい関西弁なのか、自信はないのだが。
◆予約システム入れたのに、使ってくれない!
先日、地方の倉庫団体の講演会で、「皆さんの倉庫でも、荷待ち・荷役等時間の短縮はもう、マストですよ~」とお話ししたときのことである。ある倉庫会社の社長さんが憮然として、「だからバース予約システムを入れたんだよ。だけど、言うほどの効果が出ないんだよ」とつぶやいた。
「……あんまり使ってくれないからさあ」
その通り! まさにそこが一番のツボなのだ。せっかく費用をかけて導入したバース予約システムも、ドライバーさんが使ってくれなければ意味がない。ユーザーのそんな状況を放置しているシステムベンダー側にも責任があると思うが、第一に問われるのは導入した倉庫側のリーダー、社長がどれだけ運送側の利用推拡大・定着に努力したのかである。
いくら便利そうなシステムでも、運送会社・ドライバーにしてみればPCやスマホにまた、新たなアプリを入れ、今までしていなかった「予約」という手間作業が加わるのは、単純に面倒くさい。人は「変えたくない、変わりたくない」という心理的な「慣性の法則」に、普段は支配されているからである。「そんな手間をかけて、ホントに荷待ち時間が激減するならいいけど……どうだかね~」なんていう懐疑的な傍観・様子見の姿勢が蔓延してしまうと、話は厄介だ。

◆「予約率のアップ」が成功のカギ
では同じ課題に直面し、それを見事に克服した中堅スーパーマーケット・I社の取材事例をご紹介しよう。同社が2024年にバース予約システムを導入したとき、もちろん初めに説明会を開いて運送各社に利用を呼び掛けてから、運用を開始した。ところが、以来5か月たっても、利用率は2割程度と低迷したままだった。
悩んだ部長さんが調べてみると、1つには元請けから孫請け・ひ孫請け……と重なる運送業界の多重下請け構造のせいで、実運送を担うドライバーまで、なかなか「バース予約、開始」の話が伝わっていなかったことが一因だったらしい。そもそも同社のセンターはトラック待機場所と荷下ろし場所が離れている、入荷バース数が少ない、といった構造上の課題もあり、全体の荷待ち時間は思うように下がらなかった。その過程を振り返った部長さんは、「バース予約システムは、ただ導入するだけでは効果が得られないことがよく分かりました」としみじみ述懐していた。
だがちょうどこの時期に、I社は有力スーパーマーケット各社が組織する「物流研究会」に参加していた。販売ではライバルでも「物流は協調領域」とのコンセプトで、一緒に効率化しようとの取り組みだ。でないと小売り物流は持続可能じゃない、との危機感がその背景にはある。
この研究会でI社は、先にバース予約システムを導入し成功していた先輩企業S社から、折よく適切なアドバイスを得られたというのだ。それは、①「バースの予約率向上」が成功のカギになる、②周知を頑張れば、ある日突然、予約率は跳ね上がる――というものだった。
そこでI社は改めて、実運送を担うドライバーや配送会社まで辿ってビラを配布するなど、働きかけを強化した。この努力を地道に続ける間に、3か月目から予約率は急上昇を始め、5か月目には70%超に、そして間もなく80%を超え、荷待ち時間は大きく減少した。現在では90%超を目標に活動を継続しているそうだ。……めでたし、めでたし。
◆センターキャパを超えた納品で待ちトラック行列
もう1つの要注意点にも触れておく。今度は大手日用雑貨品卸業、A社の事例から教訓を引き出そう。
同社の中部地区の物流センターは当時、トラックを最大で4時間も待たせることがあり、ドライバーや近隣から大変な不評を被っていた。朝一番に納品したいトラックが夜中から行列を作ってしまうが、接車バースは5か所しかなく、なかなか順番が来ない。交通整理もできないくらいに、ひどい状態だったらしい。一日中、アイドリングを続ける行列トラックからの排ガスにさらされる周辺住民にしたら、たまったものではない。
そこでバース予約システムを導入したのだ。しかしこちらも、即効で成果を生み出すことはできなかった。中でも同社の大きな気づきは、「センターが1日に入荷できるキャパシティに合わせて台数を計算し、予約枠を作らないと、入庫しきれず溢れてしまうことがある」だった。
これは物流センターにとって、一筋縄ではいかない問題だ。物流センター長が届く商品を発注しているわけではない。多くの会社では物流部門に受発注と在庫量コントロールの権限がないからだ。当時の物流現場リーダー・Iさんによると、「受発注には商流上の判断も絡みます。メーカーが“売上を確保したい”との意図で押し込み販売をしてきたり、また当社側が欠品の出ないようにと先々の分まで多めに発注してしまったり……発着双方の販売・調達部門の事情が優先されることがあるんです」
こうなると、受動的にその納品を受ける物流センターでは、過剰な納品量になって満杯化したり、すぐに入庫しきれないので荷役作業に手間取り、荷待ち時間がさらに伸びてトラックが長蛇の列を作り……という悪循環に陥ってしまう。物流現場に商流「不連携」の矛盾が噴き出しているのだ。
だからこそ、社内の調達・製造・販売等各部門と物流部門の連携・意思疎通が必要なのであり、加えて社外の調達先・納品先との連携・意思疎通をも担う機能として、「CLO(最高ロジスティクス責任者)」が今、荷主企業に求められているのである。ご存じの通り、改正物流効率化法で特定荷主に対して2026年度から、CLOを理想像にイメージしているらしい「物流統括管理者」の設置が義務化される。もう半年と少ししかないが、特定荷主の皆さん、準備は大丈夫であろうか?(私はかなり心配している)
ともあれA社は、Iさんが上記の問題に気付いてから、納品可能枠の設定と受け入れ可能なトラック台数の調整を開始し、懸命に試行錯誤を繰り返した末に、「やっと使える仕組みにできました!」ということだった。予約利用率を拡大することで、対象の全国28拠点の月平均待機時間は、「16分」にまで短縮したということだ。導入前は最悪、「4時間超」だったのが!
……めでたし、めでたし。
* * *
そんなわけで、IT/ソフトウェアでも、マテハン機器/物流ロボットでも、「導入すれば、即、問題解決!」なんてことは、まずあり得ない。「そんな甘いもんちゃうで!」ともう一度、繰り返しておこう。
こんな時も私たちは常に、「何のため?」を念頭に行動しないと、本質を踏み外し失敗することがある。では、「バース予約システムを導入するのは、何のため?」
それは、①荷待ち時間を減らしてドライバーの拘束時間削減=労務環境改善でドライバーのウェルビイングと定着率を改善すること、②稼働率・生産性向上を通じてドライバー不足起点の物流危機回避に寄与するとともに、③近隣社会の生活環境棄損・地球環境破壊を回避することにある。
そして、こうした仕事をけん引する物流リーダーに根底で求められる要件は、「世のため、人のため!」という使命感・責任感・志を我が物にすることだと、私は確信している。
(つづく)
【Androidでドライバーの業務管理をDX化】
オカベマーキングシステムではドライバーの業務管理を円滑にする
業務用スマートフォン・タブレットなどのAndroidデバイスを販売しています。