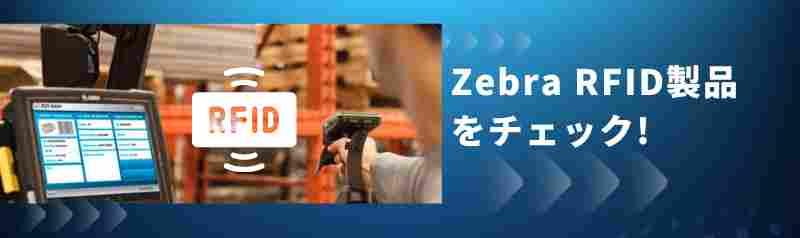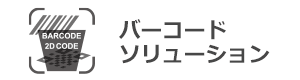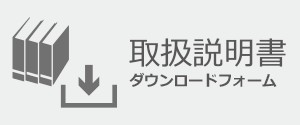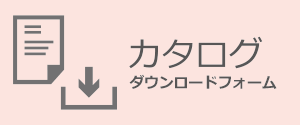- Home
- 物流ロボット導入? 高くって、ウチなんか、ムリ! <……そうとも言えない。この現実を見よう!>
物流ロボット導入? 高くって、ウチなんか、ムリ! <……そうとも言えない。この現実を見よう!>
物流ジャーナリスト・キクタの連載コラム<あるある! 物流カン違い
物流分野に漂う22の勘違いを正す!
(2025.10.15)

◆物流ロボットは高嶺の花か
物流ロボットばやりである。各地の物流関連展示会でも、多くのユーザー観客がロボットなど省力化機器やIT系の展示に集まっている。筆者もまた本コラムやあちこちの講演で、『毎年65万人もの生産年齢人口が減り続けるこれからの“超”人手不足時代、物流現場作業者は奪い合いになる』 『心理的安全性の確保と合わせ、自動化・省力化で3Kを脱却し、<働き続けてもらえる物流現場>にならないと、事業は持続可能じゃなくなる!』と訴えてきた。
そのための有効な対策の1つが、マテハン機器や物流ロボットを導入し、効果的に使うことなのだ。このことに、疑う余地はない。
しかし! である。
「物流ロボット? そんなもん高くて、ウチじゃとても、使えないよ~~(涙」
……という寂しい悲鳴が、耳の傍まで響いてくる。まあ中小事業者にしてみれば、ムリもない。今までは確かに、コスト負担力の低い中小現場にとって、ロボットなんて高嶺の花だった。
ところが! だ。
そんな消極的な認識は過去のものになり、古い常識にとらわれた「あるあるカン違い」になりつつある……としたら、どうだろう?
今回は、今も遠くにそびえる「高嶺の花」と、そうでなく、誰にも身近な「庭先の花」を合わせていくつかの実例を通し、「実際にはどうなのよ?」という皆さんの疑問に答えてみたい。
◆アスクルの大規模ロボット導入事例
まずは先進企業の物流ロボット実導入事例を見てみよう。写真1、2に示すのは「エシカルEC」を掲げて物流自動化でも国内企業をリードする大手EC事業者、アスクルがつい最近導入した最新物流ロボット。ギークプラスの最新GTPソリューション「PopPick」を一挙に444台も、ASKUL関東DCに導入した事例である。
写真1、2 アスクルが導入した「PopPick」(同社発表のプレスリリースより)

本機は有名なアマゾンの棚搬送ロボットと基本は同じく、GTP(Goods-to-Person、モノが人の手元にやってくる)タイプのロボット。ただし従来機は棚の高さが約3mで、通常5.5mの天井高がある国内のセンターでは上部空間が空いてしまい、スペース効率が悪いのが難点だった。そこで棚高さを、防火シャッター直下を通過できるギリギリの3.8mとし、保管効率を高めたのが他にない特徴だ。高すぎて人が積み下ろし作業をしにくい点は、28か所のステーションに自動入出庫装置を設けてクリア。人は出てくるコンテナから商品を出し入れするだけで、歩かない・探さない定点高効率作業ができる。
もちろんこれだけの最新自動化技術を、これほどの規模で導入するのだから、投資額は相当なものになる。公表はされていないが、億円単位もかなりのレベルだったに違いない。
◆ビームスのロボット自動倉庫
写真3、4は昨年、セレクトショップの雄、ビームスが江東区深川の新拠点「ビームス ウェアステーション」に導入したロボット自動倉庫。中国HAI ROBOTICS社製のHaiPickシステムである。本機はACR(自律型ケースハンドリングロボット)と呼ばれ、各AGVがはしご型のコンテナ自動昇降・移載装置を備え、固定設備となるスタッカクレーンはなしに、4.7m高さの保管棚からの自動入出庫を可能にする。本ロボット(57台)は棚の各エリアを回って6個までコンテナを積載、これらを写真右のワークステーションで一括・同時自動入出庫でき、高い入出庫能力を実現。普通ならこの出口直結のステーションでピッキング等を行うところ、ビームスの現場ではコンテナをコンベヤで搬送し、ソーターのインダクションで必要数をピッキングと同時にソーターに投入している。あっと驚く「ピッキングレス」運用を実現しているのが見どころだ。
基本構造としては前例と同じくGTPスタイルなのだが、ビームスの場合、1次出庫場所には人がいないので、Goods-To-Machine:GTMと言えるのかも知れない。
写真3、4 ビームスが導入したロボット自動倉庫(筆者撮影)

こちらも最新自動化技術の大規模導入事例であり、思い切った投資額が必要だったことは間違いない。大手企業がやろうと思えば、こんなことまでできる時代なのだが、中小にとってはいずれも、「高嶺の花」と言わざるを得まい。
しかし、である。昨今の技術とサービスの進化は、中小現場にも指をくわえて見ているだけでなく、広く物流ロボットの導入可能性を開いてくれつつあるのだ。
◆スミレ・ジョイント・ロジのロボットソーター
中小物流現場でのロボット導入事例として紹介するのは、埼玉県草加市に本社がある物流企業、スミレ・ジョイント・ロジの実例である。中国HC ROBOT社の「オムニ・ソーター」を、三菱商事から独立したロボットベンチャーGaussy社から一昨年に購入した。保管棚は狭いスペースに片面30×裏表の60間口をもち、作業者が商品バーコードを読んで投入すると、ロボットシャトルが自動昇降・走行して1200個/時の立体自動仕分けを行える。
写真5~7 スミレ・ジョイント・ロジのロボット自動仕分け機(筆者撮影)

同社の山口耕平社長によると、本機により作業人員を10人から2人に削減でき、1億円台の投資は3年半で回収できる見込みという。同社は年商が25億円前後の中小倉庫事業者なのだが、数年前から今後の人手不足亢進をにらんで自動梱包システムを皮切りに自動化投資を積極化。見事な成果を上げてEC物流事業を拡大中だ。この規模の小さな企業でも、社長の決意と見極め次第では物流ロボット導入を成功させられる、という証左になっている。
◆ロボットでもサブスクサービス
最後に紹介するのは、上記のGaussy社を含む複数のベンダーが提供開始している、物流ロボットのRaaS(Robot as a Service、ラース)サービスである。レンタル・リース方式のほか、物流ロボットのサブスクリプションサービス(以下サブスク)によれば、台数分の定額料金月払いでロボットを手軽に利用できる。
企業によっては短期間の単位で物量に合わせてロボット台数を増減させることが可能なサービスも出ている。従来、ロボットやマテハン機器は最大ないしそれに近い取り扱い物量に合わせて導入することが多く、少ない月には稼働率が下がって投資効果を得にくくする元凶になっていた。しかしこのサービスなら、上下する物流波動に合わせて台数を調整できるので、ムダのない投資・運用ができる。
RaaSサービス提供企業の1社、ラピュタロボティクスでは従来、AMR(Autonomous Mobile Robot、自律型自動走行ロボット)でサブスクサービスを提供してきたが、昨年、自在型自動倉庫「ラピュタASRS」でもサブスク運用を開始した。
ロボット導入の初期費用を劇的に低減し、設備の「保有」から「利用」へと転換するRaaSサービスは、中小企業の物流自動化推進のハードルを下げてくれるはずである。
写真8、9 ラピュタロボティクスのAMRとASRS(同社プレスリリースより)

以上のように、「物流ロボットは高価だから、僕ら中小企業の現場じゃ使えないよ!」という嘆き節は、今や普遍的な真理、とは言えなくなってきた。だからと言って投資効果をきちんと見極めもせず、やみくもに「ロボット導入ありき!」で突き進んだら、また失敗事例を重ねることになるから、よくよく注意が必要だ。
けれど、重い固定設備になる従来型の立体自動倉庫や大規模コンベヤ等に比べたら、近年の新進ベンチャー各社による軽量型AGV/AMR、ソーターや自動倉庫は、明らかに移設・拡張を含めた柔軟性に富み、より廉価になった。その上でサブスクほかのRaaS運用が可能になれば、投資負担力に余裕の少ない現場であっても、導入可能性は高まる。
「ウチは中小企業だけど、物流ロボット導入に成功したよ!」という事例が先の例に続いてさらに広がることを、筆者は大いに期待している。こうして「物流ロボットの民主化」が進展し、働く人にやさしい持続可能な現場が、日本の物流界の新たな常識になることを祈るばかりだ。
(つづく)
著者紹介

菊田 一郎 (きくた いちろう)
エルテックラボ 代表/物流ジャーナリスト。1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体理事等を兼務歴任。2020年6月に独立し現職。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスした著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。2017年6月より大田花き社外取締役、2020年6月より日本海事新聞社顧問(20年6月~23年5月)、同年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル顧問。
著書に『先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える』(白桃書房、共著)、『ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」』(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。
【Androidでドライバーの業務管理をDX化】
オカベマーキングシステムではドライバーの業務管理を円滑にする
業務用スマートフォン・タブレットなどのAndroidデバイスを販売しています。